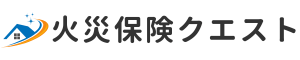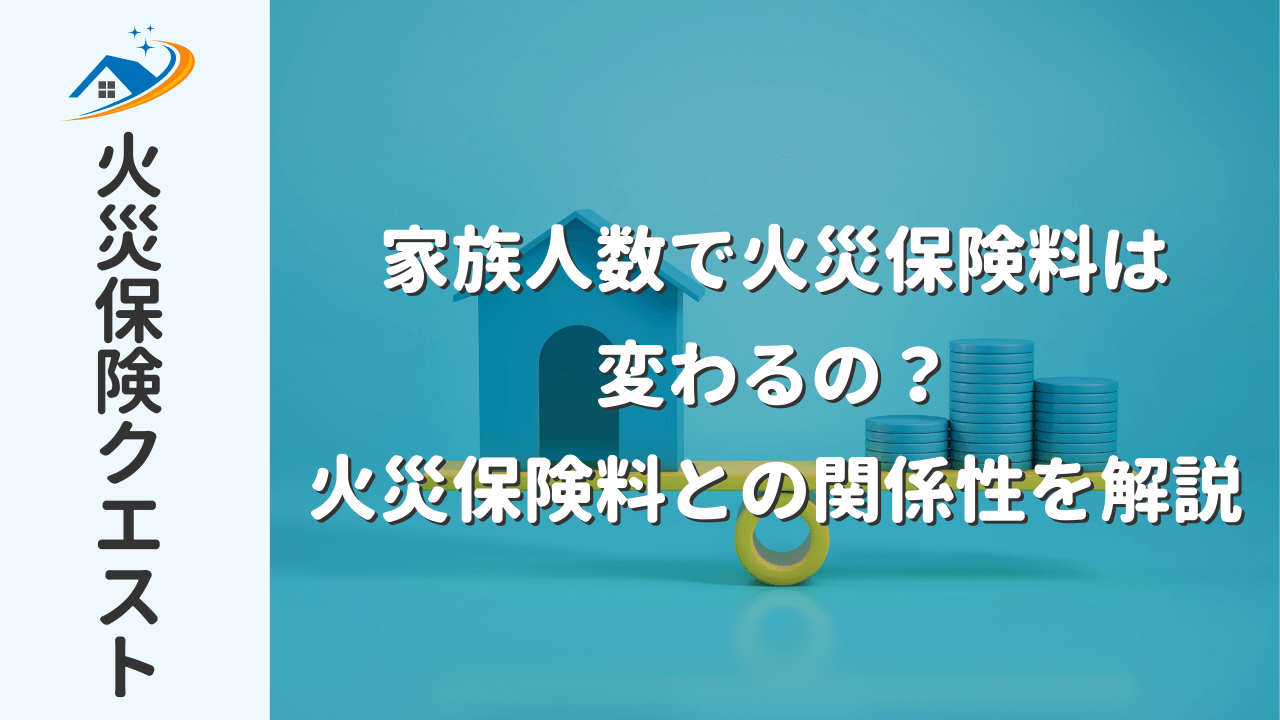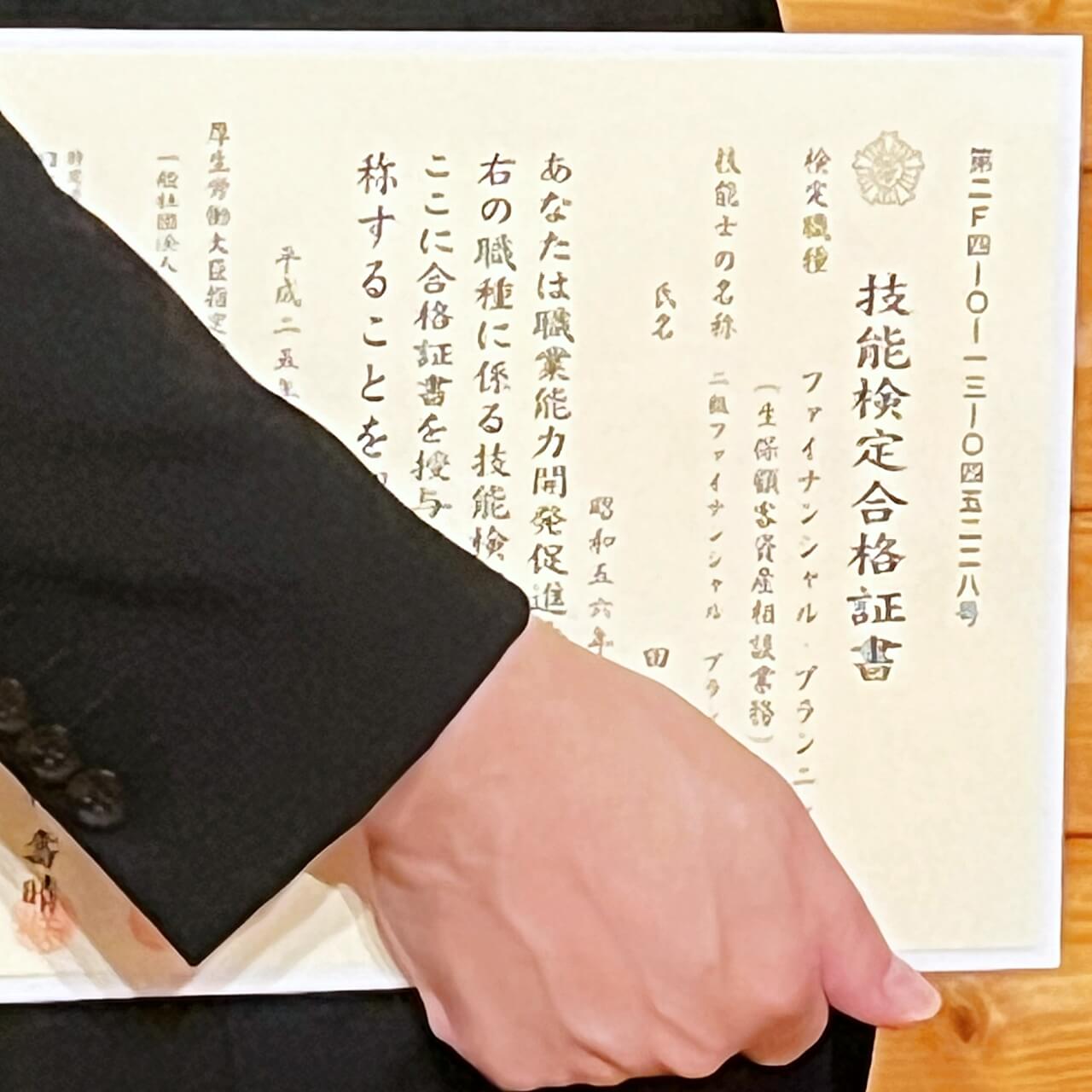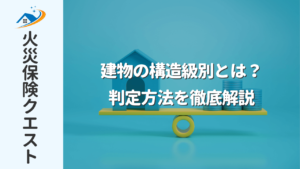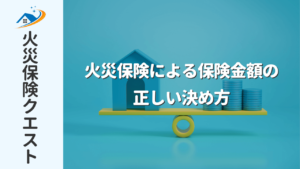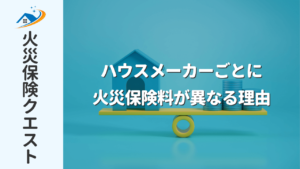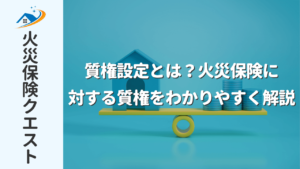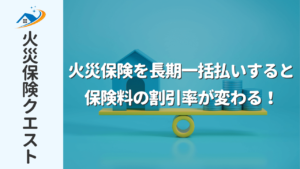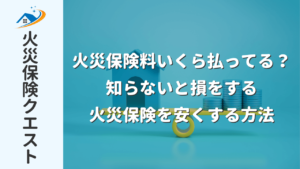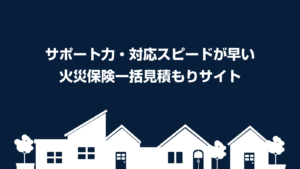火災保険に加入するとき、家族構成や同居する人数によって火災保険料が変わることがあります。
火災保険は、「建物」と「家財」が補償される保険です。
とくに家財保険の場合は、補償金額をご自身で決定することになります。
そして、家族構成や同居人数が関係してくるのも家財保険なのです。
家財保険とは?家具や家電製品など家の中にある家財に対して保険を付けること
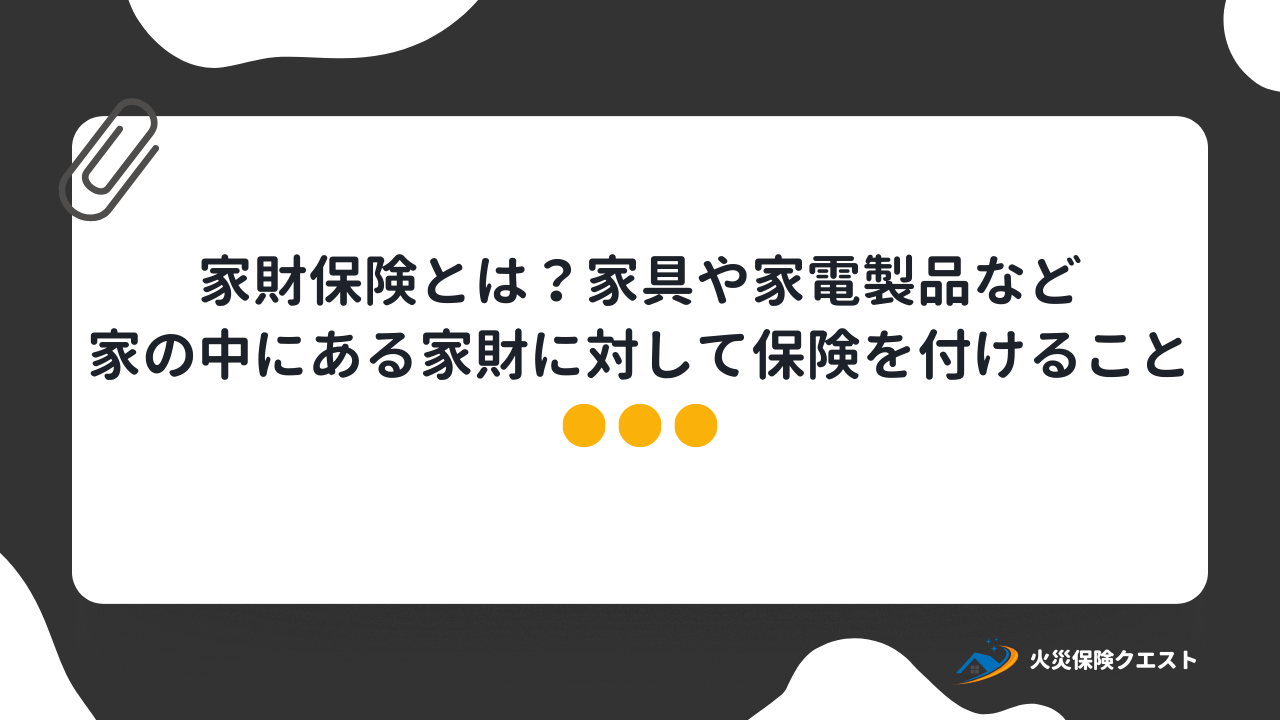
家財保険は、家具類や衣類など日常生活で使用する物に対して、災害などで損傷などを受けた際に保険金が受け取れる補償です。
例えば、テレビや冷蔵庫、電子レンジといった家電製品から、ソファーやベッドといった家具や寝具なども含まれます。
また1個もしくは1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石、美術品に関しては「明記物件」として、申込書などにきちんと明記することで補償されるケースもあります。
貴金属などの高額な家財の補償に関しては、火災保険会社によって申込方法や補償内容が異なるので、保有している人は、ここもきちんと確認しておきましょう。
家財保険の補償金額は自分で決める
家財保険の補償金額はご自身で設定する必要があります。
新築の場合では、家具や家電製品など一式買い替える人も多いかと思います。
買い替える予定がある人は家具や家電などの見積書や領収書などを保管しておき、その合計金額から補償金額を導き出すと迷わずに補償金額の設定がしやすくなります。
家財保険の金額設定については「家財保険に掛ける金額目安の決め方」の記事で解説しているので、ご参照ください。
家財保険の補償金額は火災保険更新時に見直しをしよう
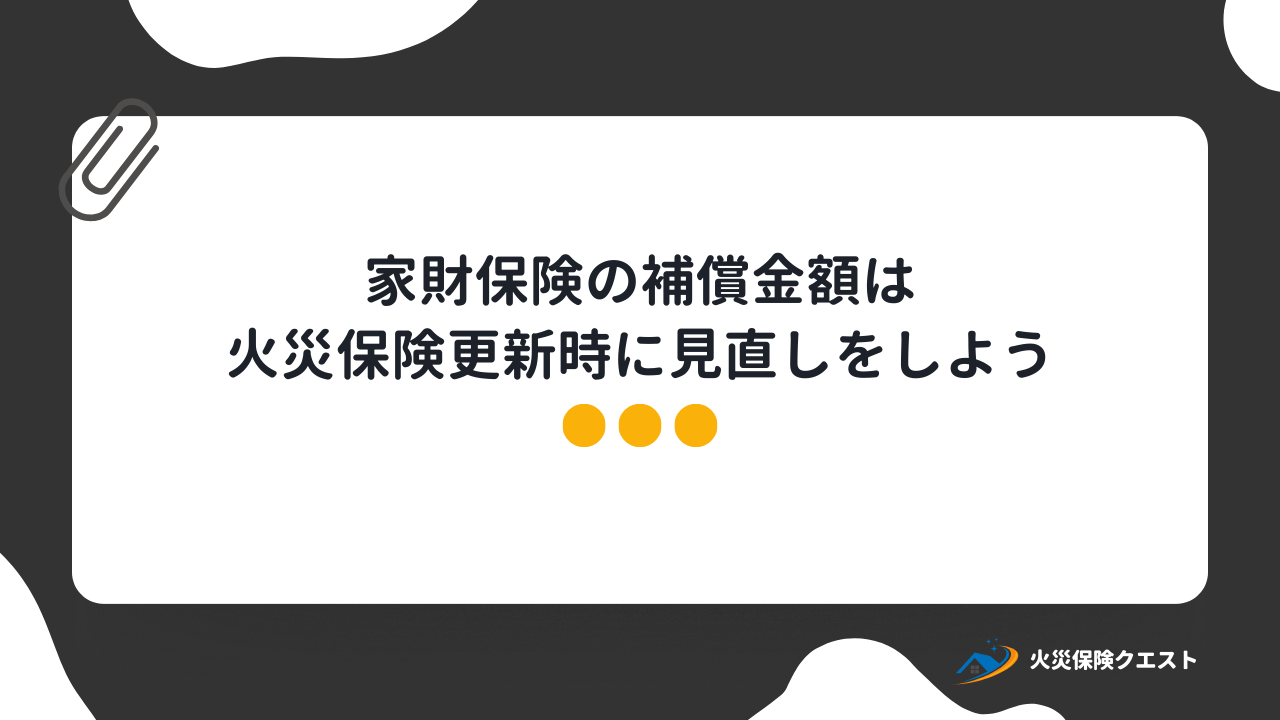
子供が増えたり、両親と同居することになった場合、家族が増えますが、一方で子供が独立して夫婦だけの生活となった場合は、人数は減ります。
住む人数が増減することで、自然と家具類や衣類、家電製品など買い足したり、処分したりすることで、火災保険加入時に設定した家財保険の補償金額にズレが生じます。
仮に人数が増えて、災害が起きてしまい家財一式を買い揃えようとしても、当初の家族構成と異なるので、不足してしまう可能性があります。
そういう事態を起こさないよう、家族構成が変わったら火災保険会社に連絡をして、家財保険の補償金額を見直すようにしましょう。
家族人数が減った場合も、家財の補償金額を減らすことで火災保険料を安くすることができます。
火災保険の契約期間が1〜5年間となるため、火災保険の更新時に見直すのもいいでしょう。
賃貸物件の火災保険の場合は家財保険は必ず付ける
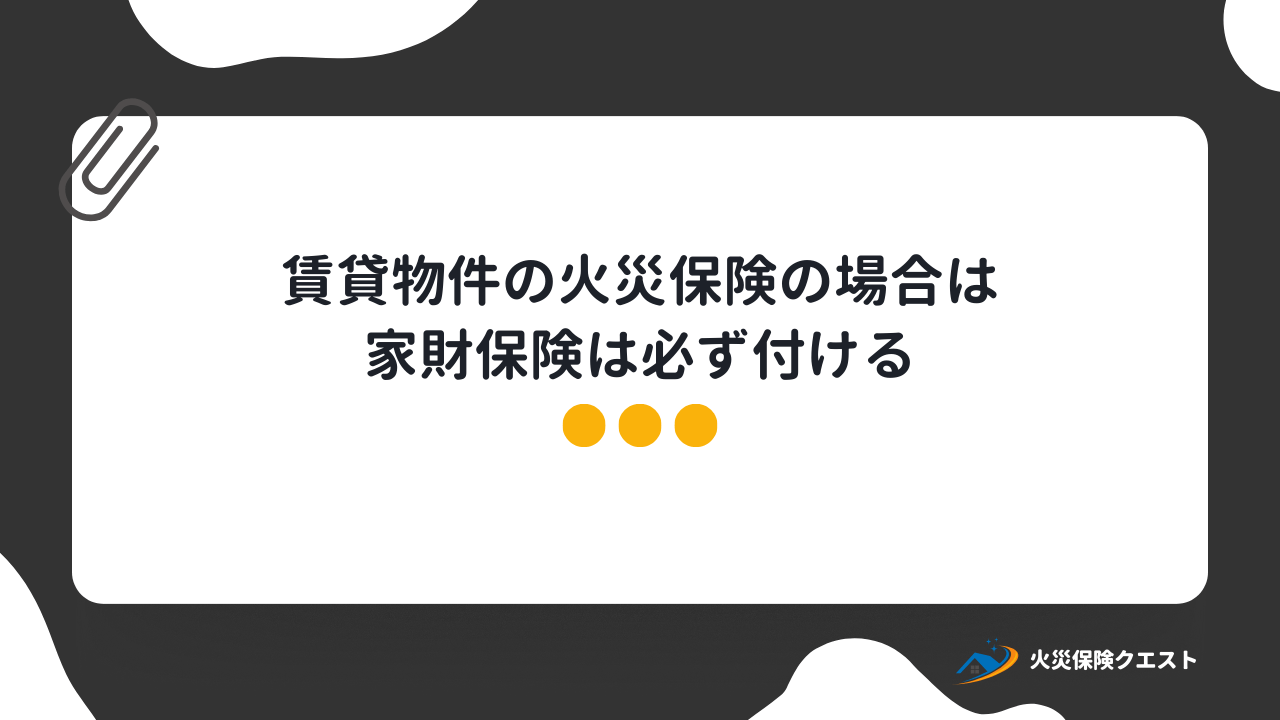
賃貸物件の場合、その賃貸契約時に火災保険が必要とされている場合が多いです。
一般的には家財に対する補償としての火災保険と、借家人賠償責任補償、および個人賠償責任補償がセットされています。
賃貸に住むことをメインにしている人の場合、その入居している部屋及び住宅は借り物ですから、部屋そのものについては建物の持ち主つまり貸主であるオーナーが火災保険の契約をしています。
その一方で、後から入居の際などに運び込んだ自分の家財道具などは、自分で火災保険の契約をする必要があります。
日本では失火責任法があり例えば、隣の部屋や家などからのちょっとした不注意から起きた火事では、例えそれがもらい火であっても隣家に賠償請求をすることはできないのです。
こうした理由から自分の家財道具は自分で火災保険をかけておく必要があります。
賃貸物件の場合は入居する人数や部屋の広さなどで固定になっている場合が多いのですが、ご自身で火災保険を契約する場合には、その保険金額は人それぞれで構わないこととされています。
入居する人はそれぞれその暮らし方は異なりますから、一律で決定できるものではないという考え方ももちろんあります。
そのため、家族構成、および部屋の広さなどに応じた保険金額を表示している保険会社もありますので、どれが一番いいかをよく判断した上で加入するようにしましょう。
まとめ:家財保険は家族人数ではなく今ある家財の総額で補償金額を決めよう
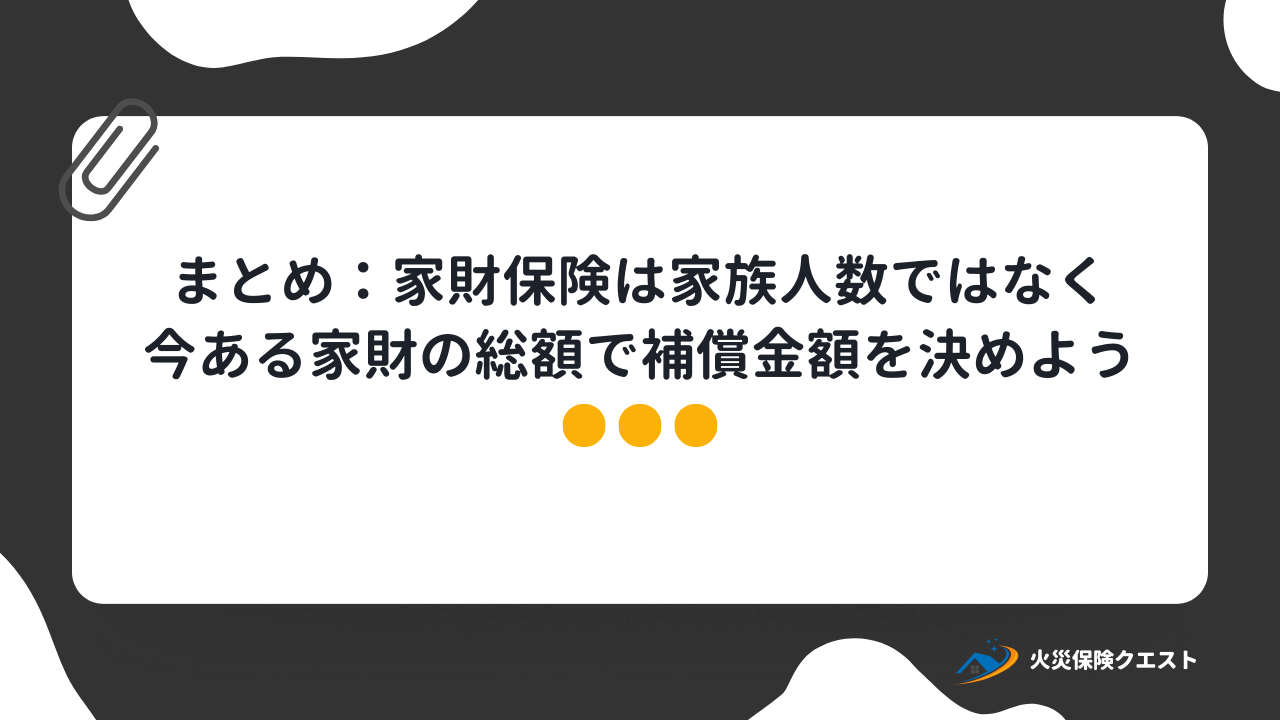
最近では、家具や家電、日用品など必要最低限して所有しない人も多くなってきました。
そのため、火災保険会社が目安としている家財保険の補償金額設定と比較すると、実際はかなり低く設定しても問題ないケースもあります。
家財保険の補償金額を決めるときは、家族人数だけでなく、実際に必要な家財の総合金額も算出して決めるようにしましょう。